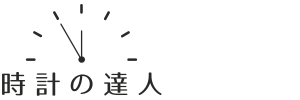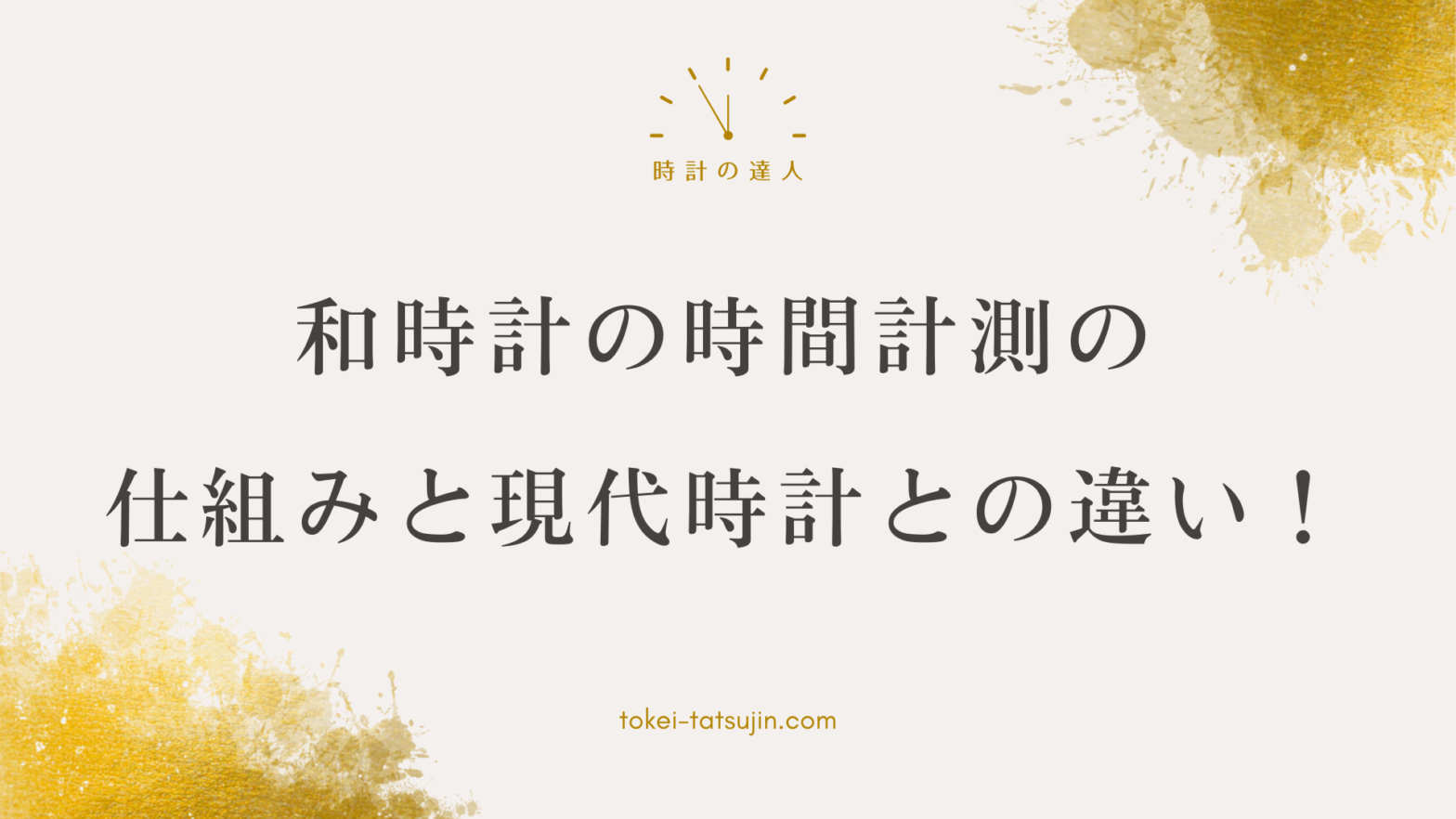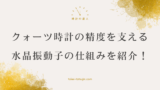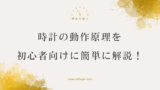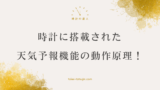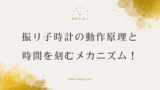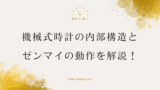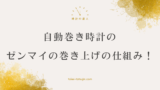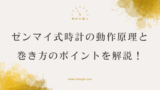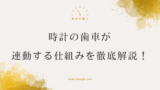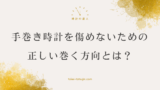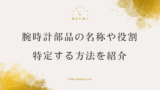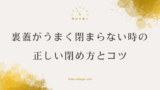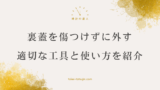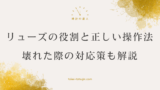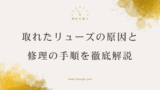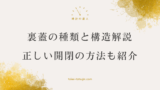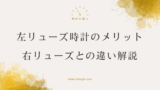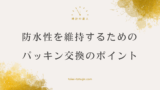この記事では、明治時代以前から日本で使われてきた和時計の仕組みに迫ります。
和時計の仕組みや生活への影響、さらに様々なモデルに至るまで、その魅力と深さを探りましょう。
和時計の仕組みについて
西洋の時計とは異なる、日本独自の「和時計」。
不定時法に基づいた複雑な仕組みは、自然との調和を重視する日本の文化を反映しています。
本記事では、和時計の仕組みや歴史、そして現代に残る魅力をご紹介します。
昼夜の長さによって刻みが変わる不思議な時計の世界へ、あなたも一緒に旅してみませんか?
和時計の仕組みとは?
まず、和時計とは何なのでしょうか。またその仕組みについて教えてください。
 質問者
質問者
 時計の達人
時計の達人
はじめに、和時計は日本独自の時間単位を使用した時計のことを指します。和時計の大きな特徴として「ひと日を六つの時分に刻む」ことが挙げられます。すなわち、日中と夜間の時間が均等に分割されるのではなく、日の出から日の入りまでと、日の入りから次の日の日の出までをそれぞれ六つに分割するのです。
おおまかに言えば、そうすることで季節によって日中と夜間の長さが変わることに対応しています。
つまり、夏の日中の時間は長く、冬の夜の時間は長くなる仕組みです。
これは、西洋の24時間均等なシステムとは大きく異なる点です。
逆に言えば、時間の長さが季節によって変わるため、一定の時間を計るのは困難でした。
この点が和時計の大きな特徴といえるでしょう。
和時計の時間の刻み方
驚きました。1日を均等に刻まないなんて。それでは、和時計はどのように時間を計っていたのですか?
 質問者
質問者
 時計の達人
時計の達人
和時計は「分刻み」という方法で時間を計っていました。これは、一定の時間が経過すると棹や鉛の重りが落下し、その音や動きで時間を知るという仕組みです。また、日本独自の時間単位である「刻」を用いています。「刻」は現代的な時間単位で言うときょうの2時間半に相当します。したがって、1日の時間を均等に分割するのではなく、日の出と日の入りの時間によって「刻」の長さが変わっていました。
出湯の煙で重りを落とす仕組みや、時鳥の鳴き声で時間を知らせるものなどもありました。
特に、昼間と夜間で時間の長さが変わるのは独特なものです。
そのため、それぞれの時間を「昼刻」と「夜刻」で区別していました。
これは西洋の24時間と違い、生活リズムや季節に合わせた時間感覚を持つ日本人特有の時間観を反映したものです。
和時計の制作技術と変速機構
なるほど、季節や自然との共生を感じます。しかし、そのような時計を作るのは難しそうです。それはどのように作られていたのですか?
 質問者
質問者
 時計の達人
時計の達人
和時計の作りは非常に高度で、時計職人の精巧な技術が詰まっています。その中で特に重要なのが「変速機構」です。この機構によって、日の長さに応じて刻の長さが自動的に変わる仕組みを作り出していました。
変速機構による可変時間制の導入は、日本の時計職人の感性と技術力が詰まったものといえるでしょう。
また、多くの和時計には文字盤が存在せず、音や動きで時間を知らされるという独特の感覚を持っていました。
そのために、和時計が時間を伝えるための音の工夫や、予想外の動きによる視覚的な楽しみを提供することもありました。
これらの工夫は、かつての日本人の豊かな時間感覚を映し出しています。
和時計の生活への影響
音や動きで時間を知るなんて、昔の人はとても豊かな時間感覚を持っていたんですね。では実際の生活において、和時計はどのように使われていたのでしょうか。
 質問者
質問者
 時計の達人
時計の達人
和時計は主に寺院や武家、上流階級の家庭で使われていました。特に寺院では、「刻鐘」と呼ばれる時計を用いて時間を刻み、一日の行事を区切っていました。また、武家や上流階級の家庭では、日常生活の時間管理に用いられていました。
和時計が使われていた時代は、生活のリズムが自然と一体となっていた時代でもありました。
そのため、日の出と日の入りに合わせて生活を行うことが一般的だったのです。
和時計によって一日のリズムが示され、人々はそれに合わせて生活していたというわけです。
様々な和時計モデル
具体的なモデルとして、どのような和時計があったのでしょうか?
 質問者
質問者
 時計の達人
時計の達人
和時計には様々な種類があり、その中でも有名なものに「柱時計」や「置時計」があります。「柱時計」は、天守閣のような垂直の柱に取り付けて時を刻むものです。一方、「置時計」は水鳥の鳴き声や龍の口から出る煙など、要所で工夫が凝らされており、視覚的にも楽しむことができる時計です。
それぞれの時計は独特の造形美を持ち、美術品としての価値も高いです。
特に「置時計」は、機械としての精密さと、装飾としての良さが融合した作品と言えるでしょう。
それぞれの時計が持つ魅力や、技術の進化が伺えます。
和時計の仕組みまとめ
さまざまな和時計と出会い、その魅力と深さに触れることができました。現代の24時間均等の時間とは違う、自然との調和を追求した時間の刻み友という考え方は、とても興味深いです。また、そのための工夫と技術の深さには驚きました。
 質問者
質問者
この記事を通して、以下の点を学びました。
- 和時計は1日を均等に分割せず、日の出と日の入りによって時間の長さを変えていた。
- 深夜あるいは早朝の「刻」を用いて時間を計り、さまざまな方法で時間を示していた。
- 和時計の設計には高度な技術があり、「変速機構」によって刻の長さを自動的に調整していた。
- 和時計は寺院や上流階級の家庭で一日のリズムを司っていた。
- 様々な種類が和時計にある。それぞれが技術と装飾の融合を体現していた。
以上から、現代の24時間制とは異なった時間観を持つ和時計について理解を深めることができました。